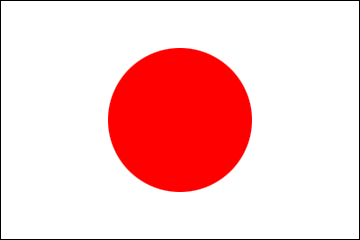【寄稿記事】「コミュニティー貯金運動」
令和元年9月4日
ドミニカ共和国の中央当たりに位置するモンテ・プラタ県ヤマサ市の山奥、エル・ランチ―トという村でJICAの元研修員のエウへニア・ベルトラン女史が「生活改善」プロジェクトの一環として「コミュニティー貯金運動」を行い、成果を上げている。ラテンの人達が貯金を始めた、と聞いて驚いた私は8月13日に視察に赴き、活動を間近で見学するとともに、参加者の皆さんに日本の戦後の焼け野原から現在までの復興と苦労の歴史を織り交ぜつつ、貯金の大切さを語り、活動を激励してきた。
サント・ドミンゴから約2時間のところにあるモンテ・プラタ県ヤマサ市ママ・ティンゴ地区のエル・ランチートという村だ。午後3時からベルトラン女史の挨拶などのあと、貯金運動のやり方を実際にやって見せてくれた。先ず驚いたのは、山奥の農民の集会が予定時間の2分前に始まったことだった。
「コミュニティー貯金運動」のやり方は次のようになる。
1つのグループの人数は最大30名として全体として目が届く人数になっている。毎週1回グループ全員がコミュニティー会場に集まり、大きな四角形の木の箱を真ん中において、4辺にある鍵を4人の中心者がそれぞれ保管している鍵を使って箱を開けて集会が始まる。この4人の中心者の1人でも欠けるとこの箱が開かず、集会が始まらない。参加者1人最低100ペソ(約220円)、最高500ペソ(貯金競争にならないようこの上限を設定)、その時々の懐具合を考えて中心者にお金を渡し、その際小さな通帳に幾ら預けたか記入してもらう。子供もお小遣いの中から最低50ペソの貯蓄が出来る。数週間すると箱が一杯になるので銀行に預けに行く。毎週の集会に遅れると50ペソの罰金をとられ、コミュニティー貯蓄に回される。
この貯蓄のお陰で各人が自分の貯蓄の3倍の額まで低利で借りられる。借り入れを希望する場合は、この集まりで借りたい旨参加者に趣旨を説明して、皆の合意を得て借り入れが可能となる。子供の学校の教材を買った、自宅の屋根を直せた、等々と皆さん嬉々として語っていた。
このような貯蓄形態は日本をはじめ他のアジアの国でも行われていたが、その様子を見ていて色々考えさせられた。一般的にはラテンの人達はその日暮らしで、給料日の数日後には殆どの現金がなくなってしまうと言われている。そのためキンセーナ(15日間)やセマナル(週間)と言われる給与の半月払いや週払いがあるほどだ。この運動により、このような幾つかの悪い習慣が大きく変わっていることが感じ取れた。先ず、一般のこの国の人にとってはかなり貴重な100ペソを毎週貯蓄して、ある時期に融資を受けることにより、お金の価値をより深く感じる習慣がつくこと、中長期的に融資を受けられることにより物事を中長期的に考える習慣がつく、汚職が社会的な大きな問題となっているこの国でお金を同じコニュニティーの人に預ける、それも相当大金を預けることにより相互信頼感が醸成される、融資をするかどうかの協議などを通じ全体の相互理解と結束心が醸成される、集会への遅刻に50ペソの罰金があることにより時間厳守、時間の重要性への認識が高まるなど沢山の効果があることが感じられた。
この貯蓄運動は中心者のベルトラン女史がJICAの研修員として、JICA筑波で実施された生活改善研修の中で得た知識を元に考案した ようだ。帰国後の2012年から始め、現在は首都のサント・ドミンゴを含めて全国に約180のグループがあるとのこと。全体の貯蓄金額も相当のものになっていると思う。
このプロジェクトはラテン系の皆さんに馴染みのない習慣を身につけ、生活を向上させる運動として非常に良いと思うので、これから積極的に広報して行こうと思っている。皆さんも是非この運動に関心を持って頂きたい。
サント・ドミンゴから約2時間のところにあるモンテ・プラタ県ヤマサ市ママ・ティンゴ地区のエル・ランチートという村だ。午後3時からベルトラン女史の挨拶などのあと、貯金運動のやり方を実際にやって見せてくれた。先ず驚いたのは、山奥の農民の集会が予定時間の2分前に始まったことだった。
「コミュニティー貯金運動」のやり方は次のようになる。
1つのグループの人数は最大30名として全体として目が届く人数になっている。毎週1回グループ全員がコミュニティー会場に集まり、大きな四角形の木の箱を真ん中において、4辺にある鍵を4人の中心者がそれぞれ保管している鍵を使って箱を開けて集会が始まる。この4人の中心者の1人でも欠けるとこの箱が開かず、集会が始まらない。参加者1人最低100ペソ(約220円)、最高500ペソ(貯金競争にならないようこの上限を設定)、その時々の懐具合を考えて中心者にお金を渡し、その際小さな通帳に幾ら預けたか記入してもらう。子供もお小遣いの中から最低50ペソの貯蓄が出来る。数週間すると箱が一杯になるので銀行に預けに行く。毎週の集会に遅れると50ペソの罰金をとられ、コミュニティー貯蓄に回される。
この貯蓄のお陰で各人が自分の貯蓄の3倍の額まで低利で借りられる。借り入れを希望する場合は、この集まりで借りたい旨参加者に趣旨を説明して、皆の合意を得て借り入れが可能となる。子供の学校の教材を買った、自宅の屋根を直せた、等々と皆さん嬉々として語っていた。
このような貯蓄形態は日本をはじめ他のアジアの国でも行われていたが、その様子を見ていて色々考えさせられた。一般的にはラテンの人達はその日暮らしで、給料日の数日後には殆どの現金がなくなってしまうと言われている。そのためキンセーナ(15日間)やセマナル(週間)と言われる給与の半月払いや週払いがあるほどだ。この運動により、このような幾つかの悪い習慣が大きく変わっていることが感じ取れた。先ず、一般のこの国の人にとってはかなり貴重な100ペソを毎週貯蓄して、ある時期に融資を受けることにより、お金の価値をより深く感じる習慣がつくこと、中長期的に融資を受けられることにより物事を中長期的に考える習慣がつく、汚職が社会的な大きな問題となっているこの国でお金を同じコニュニティーの人に預ける、それも相当大金を預けることにより相互信頼感が醸成される、融資をするかどうかの協議などを通じ全体の相互理解と結束心が醸成される、集会への遅刻に50ペソの罰金があることにより時間厳守、時間の重要性への認識が高まるなど沢山の効果があることが感じられた。
この貯蓄運動は中心者のベルトラン女史がJICAの研修員として、JICA筑波で実施された生活改善研修の中で得た知識を元に考案した ようだ。帰国後の2012年から始め、現在は首都のサント・ドミンゴを含めて全国に約180のグループがあるとのこと。全体の貯蓄金額も相当のものになっていると思う。
このプロジェクトはラテン系の皆さんに馴染みのない習慣を身につけ、生活を向上させる運動として非常に良いと思うので、これから積極的に広報して行こうと思っている。皆さんも是非この運動に関心を持って頂きたい。
在ドミニカ共和国日本国特命全権大使
牧内 博幸
牧内 博幸
○集会の様子


司会をするエウへニア・ベルトラン女史 集金(貯金)を行う木箱


集金を行う様子 参加者の発言の様子